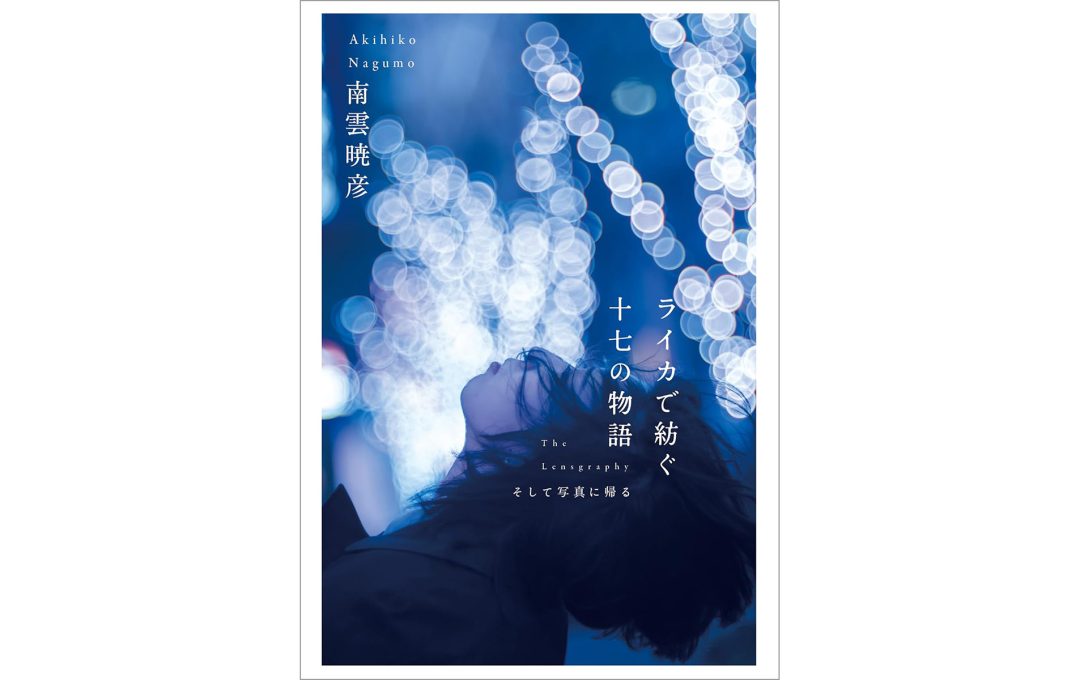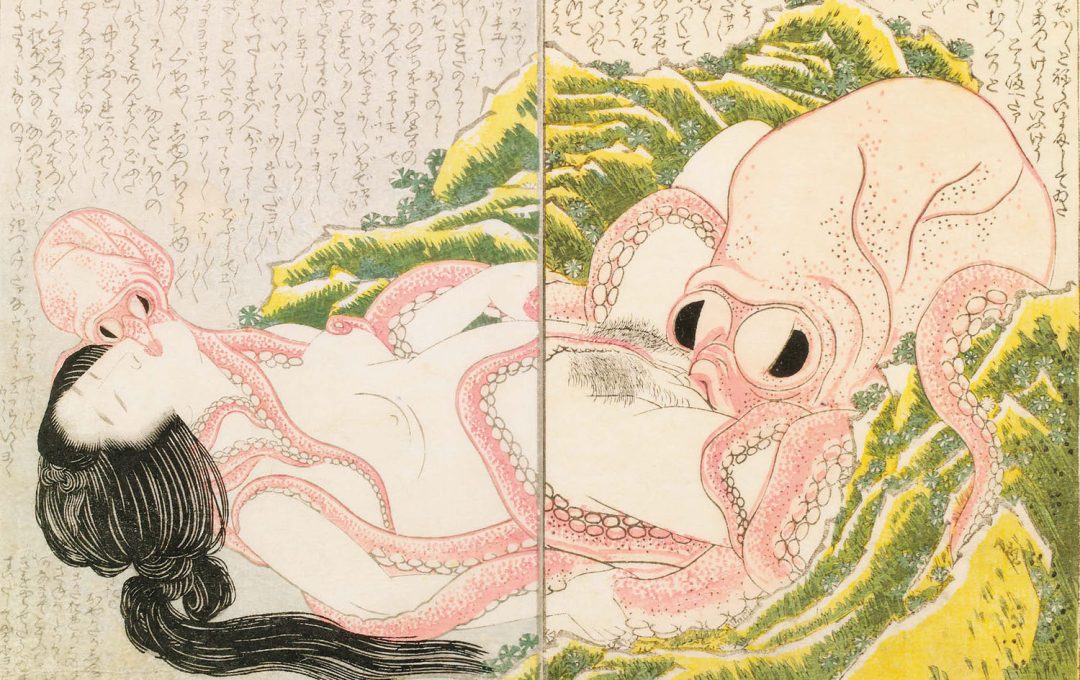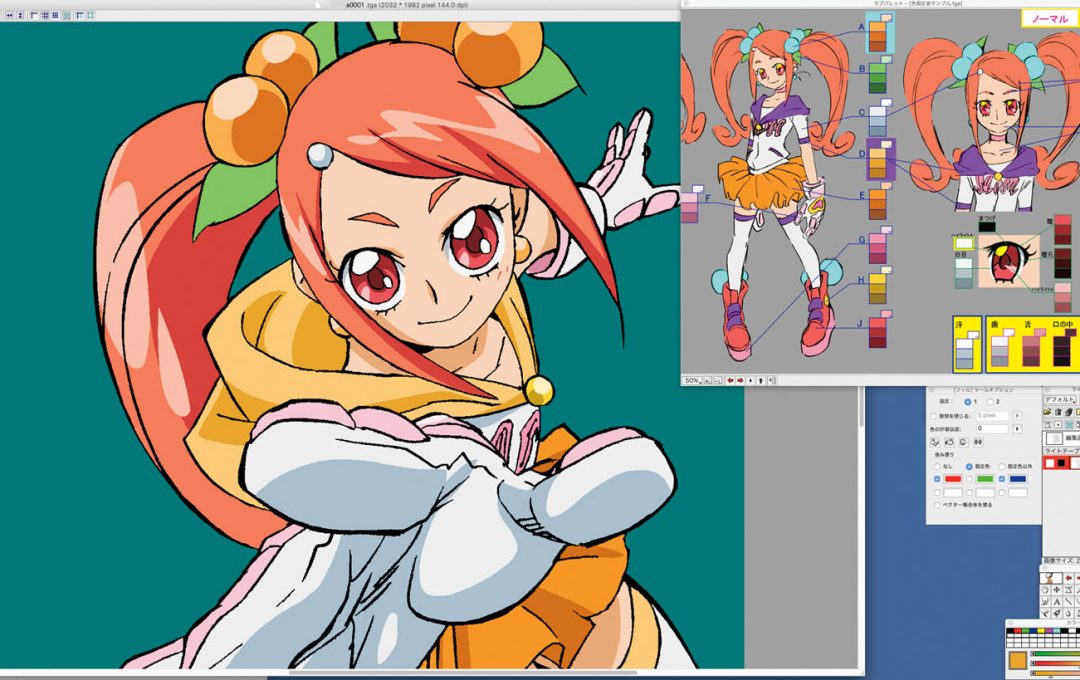写真撮影の道具たるカメラはその誕生以来、様々な進化を遂げてきました。それはカメラ自体が持つ機能だけでなく、被写体と直接相対するレンズも同様であり、長い歴史の中で、多くの交換レンズが生まれ、今なお撮影に用いられています。昨今、マウントアダプターの普及に伴って、最新のカメラで古いレンズを使う楽しみ方も広く知られるようになりました。
「オールドレンズ 銘玉セレクション」では、国内外のオールドレンズを外観写真や作例とともに紹介。そのレンズが開発された時代における新規性や立ち位置、技術的な背景など、オールドレンズにまつわる知識を深めることができる一冊となっています。
本記事では第5章「オールドレンズの世界をより一層楽しむ方法」より、プロダクトに現れる国民性について解説します。

レンズと国民性
オリジナルを突き詰める、それがドイツ流
オールドレンズを生産国単位で見ると、それぞれの国の特色が見えて面白い。まず見ていきたいのが光学大国ドイツのレンズだ。ドイツはカールツァイスやら以下など世界的に有名な光学メーカーが多く、写真だけではなく医療分野や半導体製造装置でも世界をリードしている。
ドイツのレンズの特徴は生み出す力が非常に強いことだ。1839年の写真誕生から絶えず新しいレンズを生みだし続けた。オールドレンズ界のスターレンズであるダブルガウス型、ゾナー型、テッサー型、クセノター型、プラズマート型、ガゴール型など例をあげたらきりがない。
違う視点から見ると根底に人の真似をしたくないという意思を感じる。もちろん特許という法律的な拘束もあるがそれ以上のものを感じる。例えば、ゾナーはいわずと知れた傑作レンズであるが、ゾナー型の類似レンズはほとんど存在しない。これは真似できないのではなく、意図的に真似をしていないと感じる。

ライカとコンタックスとフォクトレンダーには面白い話がある。1925年に発売された来夏に続いて発売されたコンタックスは、ライカの特許を徹底的に回避して開発された。ライカが布幕横走りシャッターを採用していたのでコンタックスは金属製縦走りシャッターを採用した。さらに皇族のフォクトレンダーはライカとコンタックスの特許を避けてプロミネントを設計した。それゆえプロミネントは「一眼式連動距離計付きビハインドシャッター式レンズシャッターカメラ」という禅問答のような方式のカメラになってしまった。
プロミネントはレンズ交換式カメラなので様々な焦点距離の交換レンズが準備されているが、一般的にレンズは焦点距離によってヘリコイドの繰り出し量が変わる。広角では少なくなるし、望遠では繰り出し量が多くなる。プロミネントのようにカメラ側にヘリコイドがある構造はレンズ交換に向いていない。しかしプロミネントの広角レンズはレンズ内でヘリコイドの繰り出し量を減らす機会的なギミックが内蔵されてある。
100ミリは光学計算のこの難題をパスした。そこまでしてでも信念を貫くあたりにドイツ人のモノづくりに関する考え方が垣間見える。反対にドイツ人は装飾的なことにあまり執着がなく、100万円を超えるような非常に高価なレンズにポリ製のレンズキャップがついていたりするあたりも面白い。
直感的な美的感覚を大切にするフランス
フランスのレンズはどうだろうか。フランスのレンズはドイツのレンズとはある意味正反対で、装飾に非常にこだわりを感じる。多くのレンズがビロード布が敷かれた専用の箱に入っている。レンズキャップはアルミ製でメーカーの刻印が入っていて美しい。鏡胴もクロームや梨地の美しいものが多く今見てもおしゃれである。反面、レンズ設計はシンプルなものが多い。しかも光学がモデルチェンジすることはほとんどない。1990年代に生産されているレンズの基礎設計が1930年代だったりすることもよくある話だ。
収差に関する考え方もフランスらしい。発生する収差を受け入れるのだ。ヌーベルバーグをはじめとするフランス映画独特のアンニュイな写りもこのあたりの考え方が少なからず影響していると思う。

師匠に学び研鑽に励む日本
最後に日本人はどうであろう。これは説明する必要がないかもしれないが、日本のレンズ設計は模倣から始まっている。これは日本の道の精神が影響しているように思う。武道でも書道でもお手本や師匠を模倣することから始まる。もちろん悪い意味ではなく道を極めるためのプロセスだ。
戦前、戦後まもなくの師匠はドイツであった。日本の設計者はドイツのレンズ設計を徹底的に基礎として叩き込んだという。その次代に現役だったレンズ設計者に話を聞いたことがあるが、会社の保管室に厳重に保管されたドイツレンズの設計図の写しがあり、新人設計者はまずその設計図を徹底的に写すことから修行が始まったそうだ。
そういう時代を経て1950年代中ごろにはそれらの改良を始めた。「青は藍より出でて藍よりも青し」という言葉がある。弟子が師を超えるのは名誉なことであり、弟子の務めという考え方である。その考え方に従い日本の光学界は戦後に大きな発展を遂げた。しかし切ないことに師匠であるドイツ人は日本人のそういった感覚が分かるはずもなく、そもそも模倣を良しとしない考え方なので、日本のレンズ設計者をよく思わなかった設計者も少なからずいたようだ。

![]()