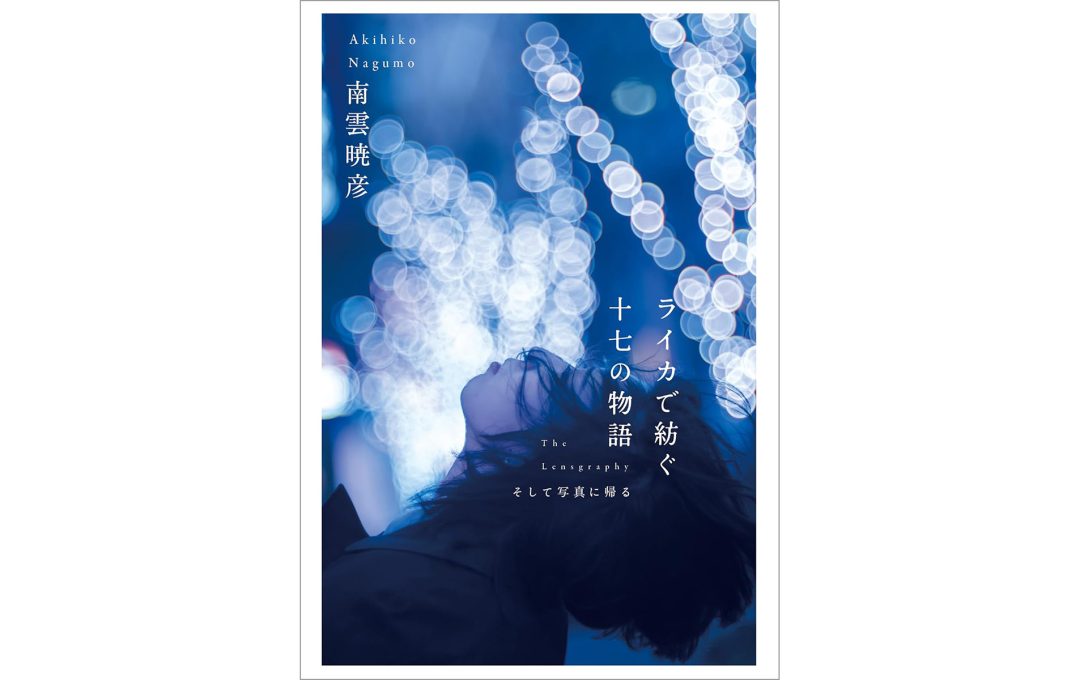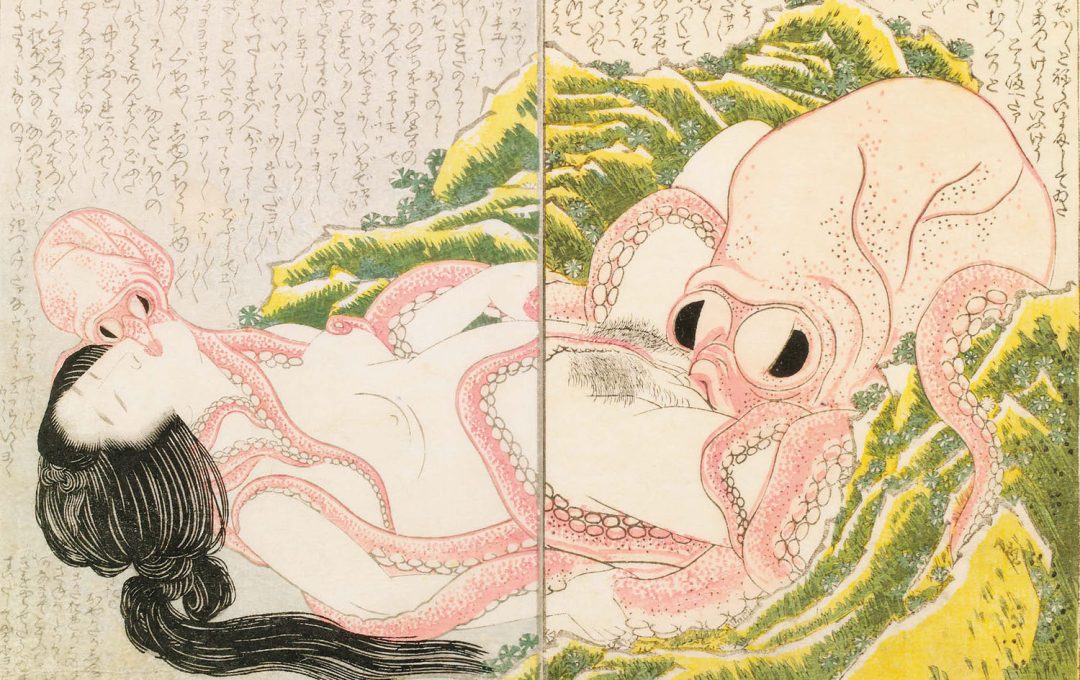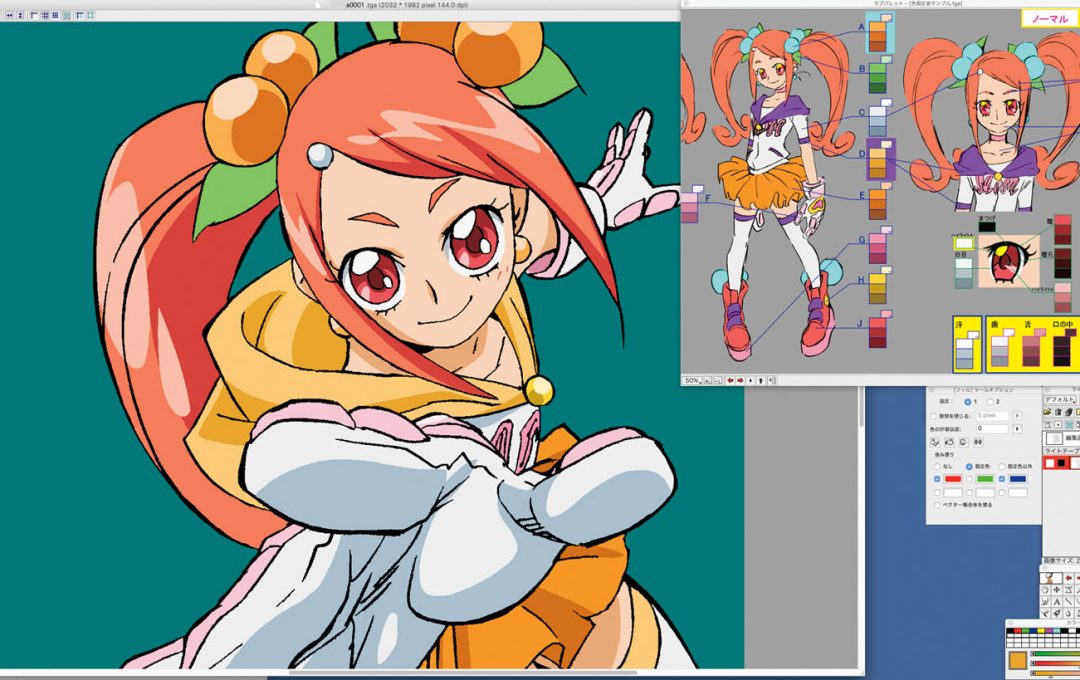かつてフィルムカメラで使われていた交換レンズは、スマートフォンで写真を撮るのが当たり前になった近年においても、カメラ好き、写真好きの人々から「オールドレンズ」と呼ばれ親しまれています。オールドレンズは「マウントアダプター」と呼ばれるパーツを用いることで現行のカメラに装着することができます。これまでに発売された膨大な数の交換レンズの中から、自分好みのレンズを見つけるのも、オールドレンズ遊びの楽しみの一つです。
「オールドレンズ・ライフ 2018-2019」に掲載している特集のひとつ、「マニアが隠れて使う名レンズ」では、シンプルに写りの良い名玉ではなく、使いこなし方を把握し、条件を揃えてはじめて楽しめる特徴的な描写を持つレンズ、ある意味「隠れ家」的なレンズを紹介しています。
本記事ではその中のひとつ、「Biotar 5.8cm F2 T」の作例と解説を紹介します。

狙い目は過渡期の大口径レンズ Carl Zeiss Jena「Biotar 5.8cm F2 T」

標準レンズのクセ玉は、いわゆる大口径タイプが主流だ。明るい標準レンズは開放で甘さが残り、それがレンズの個性として珍重される。オールドレンズ好きなら一度は試したいレンズである。惜しむらくは、大口径標準レンズは総じて値が張ることだ。
そこでマニアが目を付けているのは、過渡期の大口径標準レンズである。現在の感覚だと、F1.2~F1.4が大口径標準レンズのスペックだ。しかし、1940年代から1950年代の標準レンズであれば、F2クラスが大口径レンズだった。ここで取り上げるビオター5.8cm F2 Tも、戦後まもなくの大口径標準レンズである。
本レンズは、スタンダードクラスのテッサー50mm F2.8に対し、大口径クラスという位置付けだった。開放はシャープネスが甘く、滲みやぐるぐるボケも出やすい。当時のレンズとしては明るさを欲張っているため、開放F2という控えめなスペックの割りにクセの強い描写だ。手頃な価格の標準レンズだが、オールドレンズらしさをたっぷりと楽しめるだろう。
その一方で、堅実さも備えているのがこのレンズの良さだ。F4あたりまで絞ると、実にまっとうな写りになる。四隅まで解像し、コントラストも良好だ。安価なレンズだが、クセと堅実描写のバランスが良い。